ナンシーは叫び続けた。
周りからは変な人だと思われたかもしれない。
それでも構わず叫び続けた。
まるでこれが最後のチャンスかのように。
周りからは変な人だと思われたかもしれない。
それでも構わず叫び続けた。
まるでこれが最後のチャンスかのように。
「どうかしたの?」若い女性がナンシーに声をかけた。
「スティーブンを探しているの。」それだけ言って、ナンシーは再び叫び続けた。
女性もスティーブンの名前を呼んだ。そしてその女性に男性が声をかける。男性もスティーブンの名前を呼んだ。次々に連鎖して、色んな人がスティーブンの名前を叫んだ。
すると、向こうから「ナンシー!」と叫ぶ声が聞こえた。
しかし、「ナンシー!」「ナンシー?」と色んなところから聞こえてくる。お互いの声が徐々に近づいていく。そして、出くわした男女が声を交わした。「僕はスティーブンじゃないけど、君はナンシーかい?」「いいえ、私はナンシーではないわ。でも、スティーブンを探しているの。ある女性が。」そのようにして少しずつ声が減っていった。
「スティーブン!」
「ナンシー!」
声がひとつになり、スティーブンとナンシーはピタリと立ち止まった。
お互いを目の前にして。
そして何も言わずお互いにハグをした。
周りからは拍手が起きた。
「スティーブンを探しているの。」それだけ言って、ナンシーは再び叫び続けた。
女性もスティーブンの名前を呼んだ。そしてその女性に男性が声をかける。男性もスティーブンの名前を呼んだ。次々に連鎖して、色んな人がスティーブンの名前を叫んだ。
すると、向こうから「ナンシー!」と叫ぶ声が聞こえた。
しかし、「ナンシー!」「ナンシー?」と色んなところから聞こえてくる。お互いの声が徐々に近づいていく。そして、出くわした男女が声を交わした。「僕はスティーブンじゃないけど、君はナンシーかい?」「いいえ、私はナンシーではないわ。でも、スティーブンを探しているの。ある女性が。」そのようにして少しずつ声が減っていった。
「スティーブン!」
「ナンシー!」
声がひとつになり、スティーブンとナンシーはピタリと立ち止まった。
お互いを目の前にして。
そして何も言わずお互いにハグをした。
周りからは拍手が起きた。
「ありがとう。ありがとう。」二人は周りにお礼を言った。
しばらくしたら拍手は止み、通常の人混みへと戻った。
「や、やあ、初めまして。スティーブンです。」男性は改めて恥ずかしそうに自己紹介をした。「ナンシーよ。ふふふ。もうよく分からなくて笑えてきた。」ナンシーは顔を手で覆いながらしゃがみ込んだ。
ひとまずゆっくり話し合おうと近くのカフェに寄ることにした。
しばらくしたら拍手は止み、通常の人混みへと戻った。
「や、やあ、初めまして。スティーブンです。」男性は改めて恥ずかしそうに自己紹介をした。「ナンシーよ。ふふふ。もうよく分からなくて笑えてきた。」ナンシーは顔を手で覆いながらしゃがみ込んだ。
ひとまずゆっくり話し合おうと近くのカフェに寄ることにした。
「まるで夢みたい。」
ナンシーはまだ笑いを堪えている。
「あぁ、僕もだ。とても今、不思議な気持ち。」
スティーブンはカフェラテを口にしながら自分をリラックスさせようと必死だった。
そして、「君は僕の想像通りの人だった。」と言い、スティーブンは顔を赤くした。
「私も。あなたは理想的な人。」ナンシーも頬を染めた。
お互いに運命を感じていた。
ナンシーはまだ笑いを堪えている。
「あぁ、僕もだ。とても今、不思議な気持ち。」
スティーブンはカフェラテを口にしながら自分をリラックスさせようと必死だった。
そして、「君は僕の想像通りの人だった。」と言い、スティーブンは顔を赤くした。
「私も。あなたは理想的な人。」ナンシーも頬を染めた。
お互いに運命を感じていた。
「それにしても、あの手紙はもともと誰に宛てたものだったの?」ナンシーは思い切って聞いてみることにした。失恋の話になるのだろうと覚悟していたが、聞かずにはいられなかったのだ。
「あれはね、僕のまだ見ぬ両親に宛てた手紙だったんだ。」スティーブンからの思わぬ返事にナンシーは言葉を失った。
「僕は孤児院育ちで、親の顔を覚えていない。大きくなってから知ったんだけど、実は孤児院に預けた親は実の両親ではなかったそうなんだ。」スティーブンは続けた。
「馬鹿馬鹿しいと思うかもしれないけど、ダメもとで超能力者に親がどこにいるかを探してもらったんだ。笑えるだろ。」スティーブンはふふっと笑う。「そしたら、君の家に手紙が届いたわけだ。君が住む前の人が僕の親だったのかもしれないけど、当たっていたのか外れていたのかは結局分からないままだ。」スティーブンは寂しそうに下を向いた。
「あの…。」ナンシーはひとつ心当たりがあった。
「もしかして、あなたの本当のご両親はあなたの家の隣に住んでいるご夫婦じゃないかしら。」ナンシーは少し不思議そうに述べた。「まさか。あの夫婦は最初から子供はいないんだ。」スティーブンは鼻で笑った。
「ええ、確かに最初はそう言ってたわ。実は私、あの夫婦の家に泊ったの。しばらく話していたのだけれど、最後の日にご夫婦がこう言ったの。『実は私たち夫婦には子供が居た』って。でも、赤ん坊の頃に誘拐されてそれからずっと見つからなくて、精神的に辛いから最初から居ないことにしたんだって。」ナンシーはそう言い切ってスティーブンの顔を見つめた。
スティーブンも真っすぐナンシーを見つめた。
「あれはね、僕のまだ見ぬ両親に宛てた手紙だったんだ。」スティーブンからの思わぬ返事にナンシーは言葉を失った。
「僕は孤児院育ちで、親の顔を覚えていない。大きくなってから知ったんだけど、実は孤児院に預けた親は実の両親ではなかったそうなんだ。」スティーブンは続けた。
「馬鹿馬鹿しいと思うかもしれないけど、ダメもとで超能力者に親がどこにいるかを探してもらったんだ。笑えるだろ。」スティーブンはふふっと笑う。「そしたら、君の家に手紙が届いたわけだ。君が住む前の人が僕の親だったのかもしれないけど、当たっていたのか外れていたのかは結局分からないままだ。」スティーブンは寂しそうに下を向いた。
「あの…。」ナンシーはひとつ心当たりがあった。
「もしかして、あなたの本当のご両親はあなたの家の隣に住んでいるご夫婦じゃないかしら。」ナンシーは少し不思議そうに述べた。「まさか。あの夫婦は最初から子供はいないんだ。」スティーブンは鼻で笑った。
「ええ、確かに最初はそう言ってたわ。実は私、あの夫婦の家に泊ったの。しばらく話していたのだけれど、最後の日にご夫婦がこう言ったの。『実は私たち夫婦には子供が居た』って。でも、赤ん坊の頃に誘拐されてそれからずっと見つからなくて、精神的に辛いから最初から居ないことにしたんだって。」ナンシーはそう言い切ってスティーブンの顔を見つめた。
スティーブンも真っすぐナンシーを見つめた。
直ぐに二人は夫婦の元へと飛び立った。
そして数週間後、遺伝子検査によってご夫婦が彼の本当の両親であることが確定したのだった。
「君が手紙に返信してくれたおかげだ。」スティーブンは嬉し涙を流している。
「あなたが諦めなかったからよ。」ナンシーも涙を流した。
そして、二人は熱いキスを交わした。
終わり
そして数週間後、遺伝子検査によってご夫婦が彼の本当の両親であることが確定したのだった。
「君が手紙に返信してくれたおかげだ。」スティーブンは嬉し涙を流している。
「あなたが諦めなかったからよ。」ナンシーも涙を流した。
そして、二人は熱いキスを交わした。
終わり
13 件
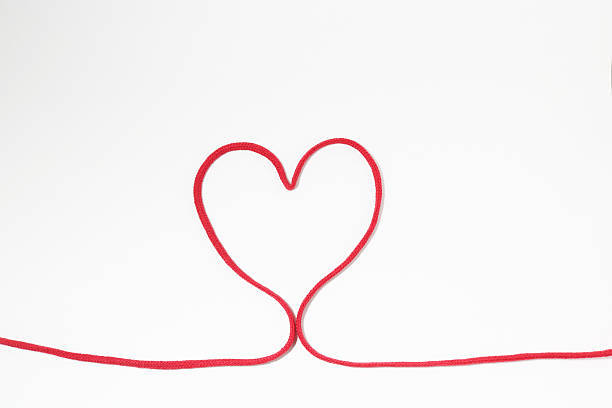










 ☆YUKARI☆
☆YUKARI☆



















